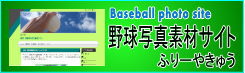関連している言葉
フリーランチ、デリバティブ言葉の意味説明
価格設定のゆがみに注目し、リスクなしで利益を得ることを目指す取引のこと本来、同じ価格であるはずの2つの商品(もしくは価格が連動する商品)に、違う価格がついているとき、
高い方を売って、安い方を買う。そうすれば、その差額分が丸々儲かることになる。
具体的には、
先物価格は、株価(先物の対象となっている元の資産の価格)に金利分を掛けた値になるはずである。
しかし、現実の価格は必ずしもそのような関係にならない。
先物価格が株価に対して割高なら、先物をショート(売る)し、株を買っておけばいいことになる。
また、身近な商品でも、場所によって価格が異なることもある。
よく、都会の物価は高く、地方の物価は低い、と言われるが、
それが本当なら、地方で物を買って、都会で売ればいいことになる。
(実際にこれをやろうとすると、輸送費や倉庫費用がかかるが…)
「経済用語サイト運営チーム編集」
経済活動での使用例
・市場参加者が多い商品ほど、裁定取引のチャンスは小さい・「せどり」とは、裁定取引の一種だ。
日常での使用例
・何回か使ったアレを見知らぬおっさんに売りつけて、同じものを買い直すという裁定取引をしたら、補導されてしまった。裁定取引に関すること
| あいうえお検索に戻る | さの言葉一覧に戻る | 経済Q&A | 新用語解説要求 |